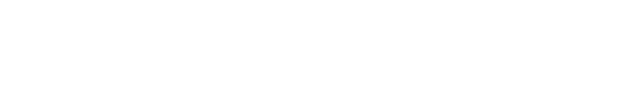全国学会での発表報告|当院リハビリスタッフの挑戦と学び
こんにちは。ホームケアクリニック麻生の院長、井尻学見です。
当院のリハビリスタッフ田澤達彦さんが「第26回日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in 群馬 2025」で発表を行いましたので、ご報告します。私も同行し、全国の医療者の前での発表に立ち会いました。
全国学会で当院の実践を発信!
この学術大会は、訪問リハビリに関わる専門職が全国から集まり、日々の実践や研究成果を共有する貴重な場です。今年のテーマは、「地域創生」〜訪問リハビリテーションの立場から誰もが暮らしやすい街を〜、2025年6月7日・8日の2日間、群馬県にて開催されました。
田澤さんが発表したのは「がん患者の在宅での看取りにおける訪問リハビリテーションの実態と課題」。当院はがん患者さんが多く、終末期の在宅支援に力を入れていることから、現場の経験をもとに取り組んだ内容です。
「限られた時間をどう生きるか」─がん患者の看取りを支える訪問リハビリの役割
当院は訪問診療を専門とするクリニックであり、在宅療養中のがん患者さんを多く担当しています。日々の現場での実践を振り返る中で、「限られた時間の中で、いかにその人らしく過ごしてもらえるか」を支えるリハビリの意義を強く感じ、今回の学会発表に至りました。
データの分析からは、がん患者さんは他の疾患の方と比べて、リハビリの開始から終了までの期間が非常に短いことが分かりました。サービス終了の理由は多くが「お看取り」であり、がんという病の特性上、リハビリの介入期間そのものが限られている現実があります。
一般的ながん患者さんへのリハビリは、病院で行われることが多いです。がん治療を継続していくと治療の副作用により体力が落ちてきます。体力低下により治療を中断する場合もあるため、体力維持のためのリハビリを行うのです。
対して、当院のがん患者は、治療をやめて自宅に戻られた方です。そのため、終末期の緩和リハビリに近いかたちになります。
多くのがん患者さんのリハビリを行っていく中で、寝たきりになる前から訪問リハビリを開始できたケースでは、亡くなる直前まで「自分で動ける」「好きなことをして過ごせる」時間が保たれていた事例が多く見られました。
寿命そのものを延ばすことは難しいかもしれませんが、「動ける期間」「自分らしく過ごせる時間」を少しでも長く保つことができたとすれば、そこには確かな意味があるのではないかと考えています。
がん患者と向き合う技術とチームの力
今回の発表を通じて、「最期までリハビリが関われること」は、当院ならではの強みだと再認識しました。多くの場面では、動けなくなると「もうリハビリはいらない」とされがちですが、当院のリハスタッフは、たとえ寝たきりでもその時々の状態に合わせたリハビリを柔軟に提供しています。
さらに、医師との日々の連携も当院の特徴です。予後の見立てや症状の変化をすぐに共有できるため、がん特有の急速な体調変化にも対応しやすく、お看取り直前まで質の高いリハビリが提供できています。
訪問リハビリの学びを地域へ|ご家族の思いにも寄り添って
今回の発表は、当院の実践しているリハビリについてを言葉にし、外に伝える第一歩でした。こうした発表は、今後の地域医療の質の向上にもつながると信じています。今後も学会発表や外部研修への参加を大切にし、常にリハビリの質を高めていきたいと思っています。
私たちの学びや成長は、地域の患者さんとご家族に還元されてこそ意味があります。最新の知見や技術を、実際のケアに生かし、「このクリニックを選んでよかった」と思っていただくため、在宅医療だけではなくリハビリの側面からも届けていきたいのです。
患者さんやご家族が選んだ「在宅での暮らし」という選択に対して、私たちは医療・看護・リハビリそれぞれの専門性を持ち寄り、最期までその人らしい時間を支える力になれるよう努めてまいります。
ホームケアクリニック麻生の井尻学見でした。